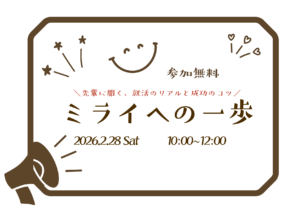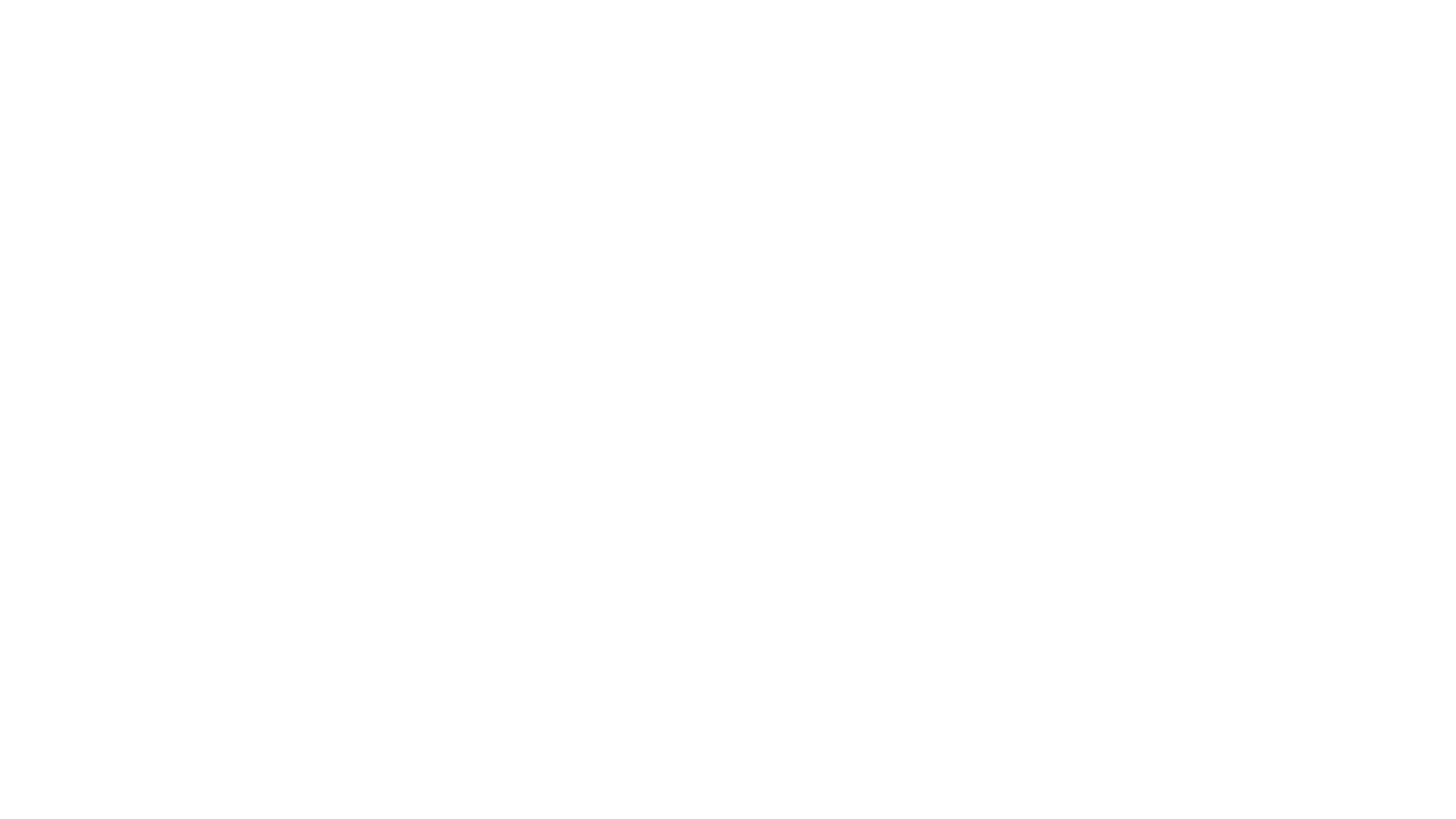こんにちは(^^♪天王寺の車谷です。
もう、5月も中盤に差し掛かっておりこれから夏に向かってという時期かと思います。
花粉もなくなり、すこぶる良い状態の車谷です。

さて、今回は季節の話とはうって変わりCONNECT天王寺で行っている「認知行動療法プログラム」についてシリーズ4部作にわたってご紹介したいと思います。
今回は記念すべき第一回目です。

皆さんは「認知行動療法(CBT)」という言葉を聞いたことがありますか?
近年、メンタルヘルスの分野だけでなく、日々の生活現場でも注目されている心のトレーニング法です。又、スマホのアプリにも導入されているのも皆さんご存知でしょうか?
CONNECT天王寺では、仕事に向かううえでの「不安」や「自己否定感」、「人間関係のストレス」など、心の中のさまざまな課題に向き合う機会があります。
そんなとき、自分の「考え方」や「感じ方」のクセに気づき、それを少しずつ変えていくことで、気持ちが軽くなったり、前向きな行動につながったりする――それが認知行動療法の大きな特長です。
今回は、当事業所で取り組んでいる認知行動療法プログラムの内容や、利用者さんの変化、日常生活にも活かせる考え方のヒントを、わかりやすくご紹介していきます。
今回のラインナップです。
目次
1. 認知行動療法ってなに?
2. 認知(考え方)と行動の関係とは?
3. なぜ就労支援に効果があるの?
4. 当事業所での取り組み
5. 最後に
認知行動療法ってなに?
就労支援に活かされる「心のトレーニング」について解説!
みなさんは、日常生活の中で「うまくいかないな」「自分はダメだな」と感じることはありませんか?
そんな時、実は“考え方のクセ”が気持ちや行動に影響していることがあります。
「認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)」は、そうした思考や行動のパターンに気づき、自分にとってより良い形に少しずつ変えていくための心理療法です。専門的な知識がなくても、日常生活や職場で活かせる実践的な方法として、就労移行支援の現場でも注目されています。
認知(考え方)と行動の関係とは?
たとえば、こんな場面を想像してみてください。
「上司に挨拶したけど返ってこなかった。嫌われてるのかもしれない…」
→ 気まずくて、その後話しかけるのをやめてしまう。
このように、**「相手の反応」→「自分の考え」→「気分」→「行動」**という流れで、私たちの行動は影響を受けています。
でも、もしかしたら上司はただ忙しくて聞こえなかっただけかもしれません。
CBTでは、このような「自動的に浮かぶ考え(自動思考)」に気づき、別の視点や現実的な捉え方を学ぶことで、感情や行動をよりよい方向へ変えていきます。
なぜ就労面で効果があるの?
就職活動や職場での人間関係は、誰にとっても不安やストレスのもとになりやすいものです。
特に、過去の経験から「どうせ自分には無理だ」「また失敗するに違いない」といった思考のクセを持っている方にとっては、一歩踏み出すのが難しく感じられることもあります。
認知行動療法を取り入れることで、「自分の考え方に気づきやすくなる」・「ストレスを客観的に見つめられるようになる」・「できたことや前進を意識できる」・「他者の言動を悪く捉えすぎない習慣がつく」といった変化が見られるようになります。
これらは、就職活動だけでなく、働き続ける力=「職業的自立」にもつながります。
CONNECT天王寺での取り組み
CONNECT天王寺では、月に2回、認知行動療法をベースとしたグループワークを実施しています。
写真のように1週は動画視聴、ワークシートの記入。2週目はグループワークの実施(利用者同士で日々ネガティブに感じた出来事をシェアしていただいています。第1回では、各々の出来事に直面したときの感情についてフォーカスしシェアしています。)
グループワークにも参加することで、少しずつ「気づく力」が育ち、考え方や受け止め方が柔らかくなることで、「自信がついた」「前向きになれた」といった声も多くいただいています。

最後に
認知行動療法は、特別な人だけが使えるものではなく、誰でも生活の中に取り入れられる“心のストレッチ”のようなものです。
「こんな考え方もあるんだな」「ちょっとやってみようかな」――そんな気軽な一歩から、変化は始まります。
次回のブログでは、第二回で行っている内容や今回お話しできなかったことまで詳しく紹介したいと思います。
それではまた。